13年ぶりの子持ち権現「ホンガケ道」 (エントツ山登山記)
2020年6月20日

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 瓶ヶ森〜釜床谷〜鳥越〜子持ち権現〜三角点「子持」〜瓶ヶ森

通常の登山とは違い、一旦鳥越まで下ってから子持ち権現へ本懸(ホンガケ)道を登り返す
プロローグ
掲示板投稿者の「六甲山のキセキ」さんから最近子持ち権現ホンガケ道に関する問い合わせがあった。13年前に2度マーシー
さんと歩いているがもう細かい場所の記憶が定かでは無い。
そこで、の〜ちゃんに続き犬返仲間の黒河ジュニアさんもテントを買ったって言うので瓶ヶ森でテント泊と子持ち権現ホンガケ道
をセットにして歩く事にした。
朝、山根運動公園を7時集合で瓶ヶ森駐車場へ付き、先ず第一キャンプ場へ行く。既に2組程テントが張られていたので、一番下
の広場にてテントを設営する。黒河ジュニアさんは能智さんと同じアライテントのトレックライズ、私はファイントラックのカミノ
モノポールシェルターの初使用だ。マーシーさんはブラックダイヤモンドの青いストックシェルター。で、の〜ちゃんはと言うと
テントをザックに入れ忘れて来てマーシーさんの予備ツェルトを張る事になった。
.jpg)
.jpg)
瓶ヶ森駐車場から一旦第一キャンプ場へ向かう 下の広い場所にテント・ツェルトを設営する
.jpg)
.jpg)
黒川ジュニアさんのアライテント トレックライズ マーシーさんのBDストックシェルター の〜ちゃんテント忘れる!
奥は私のファイントラック カミナモノポールツェルト
その後、一旦瓶ヶ森駐車場に帰って日帰り装備で子持ち権現ホンガケ道へ向かう事にする。
子持ち権現ホンガケ道とは

石土山(瓶ヶ森)別当寺 石中寺のHPより抜粋

同じく 石中寺のHPより 子持山と石土山(瓶ヶ森)
瓶ヶ森は古くは「石土山」(いしづちさん)と呼ばれる修験の山だったらしい。瓶ヶ森林道が開通した今は実にお手軽な山となって
しまったが、それ以前のルートは西之川から名古瀬谷〜十郎アレ〜常住を通り鳥越峠に出る。
そこから厳しい釡床谷を上がって瓶壺へ至るか、少し東側へトラバースし子持ち権現山の西尾根岩峰を這い上がり一旦子持山を経て
瓶ヶ森男山(石土山)へ至るかどちらかのルートだった様だ。
事実、西条側から見る瓶ヶ森は、瓶林から即氷見二千石原のなだらかな笹原のイメージは無く、隆起準平原を支える厳しい岩峰が立つ
難攻不落の山城の如くいかつい山の様相を成す。
この厳しい岩壁を見ると、ここが石土山として古来より山伏達が修験の為に通った霊山と言う事が理解出来る。更にこの修験の質を
高める為に子持ち権現ホンガケ道が作られたと思われる。ホンガケは恐らく修験的に「本懸」或いは「本駈」だろう。つまり、ここ
がメインの修験のルートよ!って意味?
子持ち権現ホンガケ道は鳥越から東にトラバースして子持ち権現山の西尾根に取り付き鎖場を辿って山頂へ、そこから又鎖場を下っ
て瓶ヶ森男山(旧・石土山)へ至る修験の道である。

子持ち権現本懸(ホンガケ)道 ここに石中寺の信者さんによって大正14年頃敷設された鎖場がある
石土山(瓶ヶ森)修験道
石鎚(石土)信仰のルーツは瓶ヶ森? 石土蔵王権現を巡る攻防
瓶ヶ森は古来「石土山」と呼ばれて西条市黒瀬にあった「天河寺」(てんがじ)が山や修験者を管理する別当寺であったと言われ
ている。このお寺跡には私も行った事があるがあの有名な役行者が大和時代にこの上にある龍王山で修行を積み石土蔵王大権現を
感得し、すぐ下の平地を選び「天河寺」を開基したという話がある。
室町時代末期に戦火による大火災に遭い消失した時に当時の弟子が法灯を持って山を下り極楽寺を建てたと、そのお寺の話に出て
くる。
又、奈良時代に行基によって石土山(瓶ヶ森)が開山されたという話もあるぞ。この行基さんや役行者さん、弘法大師さん達はどこ
にでも話に出てくる。ようわからん昔の話は大体が権威付けの為に盛って語られるのが世の常だ。
西条市のHP・加茂の歴史に上野さんが深山灌項系譜を引用し「役小角の門弟「芳元」が大和峰山修行をし
、西暦735年(養老
3年)に伊予に帰って、西暦737年(天平9年)から瓶ヶ森に祀っていた石鎚の神を石鎚山へ奉還して祀りたいと申したが、神宮寺
の天河寺の反対で実現できず、芳元は石鎚山へ熊野権現を勧請し」たと記されている。(年代のつじつまが合わないがまあ、古い
話なので大目に見よう)これが石鎚神から石鎚蔵王権現となる転機なのであろうか?
そして更にダメ押し的な話として「西暦828年(天長5年)に、芳元の門弟が瓶ヶ森の石鎚の神を、芳元の遺訓によって背負って
石鎚山へ奉還されたことによって、黒瀬の天河寺より龍王山を経由し瓶ヶ森へ行く参拝道の利用者は大幅に減少しました。」とある。
この門弟とは「石土蔵王権現」を背負って石鎚山へ持って来てしまった西条・西之川の庄屋「高須賀家」の先祖だと言われる話だ。
石鎚側ではそれを奉還とか良い言葉を用いるが瓶ヶ森側からすればそれは「持ち去り」と言えなくも無い。兎に角、その事件以来
石土蔵王権現信仰は瓶ヶ森から石鎚山へと移って行ったという事だろう よう知らんけど・・・
「石土山(瓶ヶ森)修験道」は昭和初期に今治の「石中寺」(いしなかてら)68世住職小笠原観念という人が中心となり修験道
を復活させる。そして石中寺は戦後に天台宗三井寺門派から独立して「石土宗」を興し、「石土山修験根本道場」を創設した。
一方、小笠原観念の弟子・松浦観舜さんが昭和14年天台宗因島・石土教会を設立し、戦後(S22年)天台系本山派「光明寺」
を創設し、修験道の「験乗宗」を名乗った。
かくして、瓶ヶ森の修験道は天台宗系である今治の「石中寺」と因島の「光明寺」によって戦後再興されたと言える。確かに子持
ち権現ホンガケ道を歩いていると因島の光明寺と記された表札が見受けられる。
子持ち権現ホンガケ道に鎖が懸けられたのは大正14年らしいからそんなに古い話では無い。石鎚山の鎖は江戸時代初期に懸けられ
たと言うから鎖禅定に関しては石鎚山の方が歴史が古い。
子持ち権現山と瓶ヶ森・男山の鎖は大正末期から昭和初期に瓶ヶ森修験道をの復活に燃えた前出の石中寺住職・小笠原観念さんが
中心になって信徒と共に敷設したと思われる。鎖には寄進者の名が刻まれており、修行の目的(鎖禅定)であっただろうが、これが
無ければ我々も子持ち権現に西条側からおいそれと這い上がるのは非常に難しかっただろう。
前置きが長かったが、やっと本題の子持ち権現ホンガケ道の山行記に入るぞ!
行程1)瓶ヶ森駐車場〜瓶壺〜釡床谷〜鳥越 約1時間35分
10時35分テントを張り終えて駐車場に帰り、改めて子持ち権現ホンガケルートへと出発する。10分程で瓶壺分岐標識を瓶壺
に向かって進む。左手に筒上山と箱山が見え、その手前に子持ち権現山が見える。グルっと北側から回り込んであそこに行くのだ
と初参加者に説明する。石鎚の北側は雲海が広がり、成就社とその向こうに三ヶ森が雲の上に顔を出している。
10時54分瓶壺・西之川分岐標識から石鎚を正面に見て笹原の登山道を下と白骨林が3本をバックに石鎚の最もポピュラーな形
が見える。

手前にこれから行く子持ち権現と奥には筒上山・手箱山
.jpg)
氷見二千石原の笹原を瓶壺に向かって下る 右に石鎚成就社とその向こう奥に三ヶ森が雲海に浮かぶ
11時00分瓶壺に下りる。瓶ヶ森の山名はこの瓶壺から来ているとの説もあるが、良く分からない。事実ここの三角点名は
「亀ヶ森」と付けられている。昨日の雨で水が瓶ヶ森斜面から勢いよく流れ落ちて枯れた植物の茎が瓶壺に浮いて回っている。
とても滑り易い徒渉部を恐る恐る渡り釡床谷へと向かう。
.jpg)
.jpg)
瓶壺・西之川方面へ下る 11時00分 瓶壺に着く 水は補給しない
瓶壺に集まった水は北側の瓶壺谷に向かって流れており、1,661mピークの支尾根が分水嶺になって釡床谷へは流れて行かない。
登山道は先ほど先行した5〜6人の作業グループにより綺麗に刈り払われており恐縮する。瓶壺から鳥越まで標高差500m弱を
一気に下るのだが、途中木の梯子段やロープなどで登山道は良く整備されている。
.jpg)
.jpg)
西之川への登山道は朝会った有志の方達が笹刈りをしてくれていた 瓶壺の水は北側の瓶壺谷へと流れて行く
.jpg)
.jpg)
大岩付近からいよいよ釜床谷の劇下りが始まる 道は整備されているので歩き易い
.jpg)
.jpg)
木の梯子段は濡れているので滑り易い 草地の急傾斜を下る
.jpg)
.jpg)
ロープや木の階段で整備された登山道 釜床谷をどんどん下って行く
11時18分右手に大きな岩の洞があるが、特にここで祭礼などが行われている様な痕跡は無い。釡床谷は自然林の緑が広がり、
古木にツルアジサイが巻き付き花を咲かせて雰囲気の良い場所である。下の方で草刈り機の音と人の声がして、草刈り作業をして
いる方達に挨拶をして先に行かせて貰う。
.jpg)
.jpg)
岩窟が右手に有ったが中には何も祀られていない このデカい蒲鉾岩は記憶がある
.jpg)
.jpg)
要所に西之川への標識が立っている 正面に手箱・筒上・岩黒が見える
.jpg)
.jpg)
すり鉢状の谷だから釜床谷って名前が付けられたのかな ヒメシャラが現れると植林帯になる
ヒメシャラの立つ自然林を下ると植林帯に変わり、12時11分「鳥越」に到着した。標識には西之川まで3.1kmとある。
5分程辺りを見学しながら写真休憩を取る。ニョキっと突出した特徴的な鳥越岩に見覚えがあった。昔はここに茶店があったとか
で確かに建物が立っていた様な平たい場所がある。
.jpg)
.jpg)
12時11分 平らな場所に着いた 「ここは鳥越」の標識が立っている 初めて訪れる二人
.jpg)
独特の形をした「鳥越岩」 ここが子持ち権現本懸(ホンガケ)道の分岐となる
行程2)鳥越〜兵平岩〜尾根分岐〜子持ち権現山 約3時間30分

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 子持ち権現本懸(ホンガケ)道
A)鳥越〜尾根取り付き部まで約1時間10分
鳥越峠から東側の植林帯に薄い踏み跡が残っている。「通行止」や「立ち入り禁止」と書かれてロープが張られているので余計に
進むべきルートが分かる。恐らく鎖が古いので安全性が保障されていないって事だろう。ここからは自己責任で歩くルートである
事を自覚して気を引き締める。二ッ岳にある三島警察署の「ここから先は命懸け」という標識に通じる標識だ。
12時22分禁断のロープを潜って修験道へと足を踏み入れる。霧が覆う樹林帯を薄い踏み跡を辿ってほぼ水平に進む。


12時22分 いよいよ子持ち権現本懸(ホンガケ)道へ踏み込む 踏み跡は有る様な・・・無い様な・・
兵平岩? 平兵衛岩
?
12時30分石がゴロゴロした沢に突き当り少し沢に沿って上がる。すると因島光明寺石峰団「兵平岩」(先達供養塔)の標識
がありちょっとした岩っぽいガレ沢を渡る。平坦な岩が多い場所なのでルートは少し不安だが直ぐに「石土山参道」の標識が木
に掛けられていた。更に「兵平岩」の標識があり12時35分薄暗い霧の中から縦長いデカい岩が現れる。奥に回り込むと大岩の
下の抉れた部分に先達のお墓やら石塔が沢山立っていた。
「兵平岩」ってどうも変な名前だと思っていたら、赤いクレバス君が因島光明寺へ出かけた際のレポで昭和5年発行の「霊峰石つ
ち山」その他には「平兵衛岩」と記されていると調べている。さすが石鎚研究家だ! 恐らく光明寺石峰団の方が標識を作る際
に石中寺でも通称になっている「兵平岩」を採用したのだろう。こういう間違い(?)が長い歴史の流れの中で定着する場合が多い。
.jpg)
.jpg)
ちょっとした崩壊地の上側を抜ける 12時30分右手に沢が現れ、少しそれに沿って進む
.jpg)
.jpg)
兵平岩への標識がある(因島光明寺石峰団) 直ぐにちょっとしたガレ沢を渡る
.jpg)
.jpg)
石土山参道の標識 (比較的新しいのか、まだ字が読める) 兵平岩の標識 こちらはいつまで持つかわからない

.jpg)
確かにデカい岩がある 12時35分 兵平岩に着いた様だ

兵平岩とも 平兵衛岩とも言われる大岩の下には供養塔が立っていた 奥へルートをチェックに行くが分からず引き返す
兵平岩の奥に道が無いかチェックに行くが水が少し流れる沢があって良く分からない。スマホ地図をチェックすると破線ルートは
大岩の上側を回り込んでいる。兵平岩は修験ルートから少し外れた祈祷所となるので引き返して大岩の上側へと回り込む。テープ
や標識に従って岩が転がるワイルドな場所を進むが地図の破線ルートより少し上側を巻いていた。
12時53分アルミの標識があり直ぐ涸れ沢を渡る。標識に従い次の涸れ沢を渡ると左手の岩に標識が掛けられていて13時00分
地図の破線道に合流した。そこからも小木が生えた自然林をトラバースして行くと13時10分明るいザレ場を通りかかり、ここ
で簡単な昼食タイムとする。
.jpg)
.jpg)
大岩の上に大きく回り込むと赤テープも見られた 確かにこの辺りは道の様に見える
.jpg)
.jpg)
12時53分 標識が岩の上に置かれている こんなアルミの標識が置かれている
.jpg)
.jpg)
涸れ沢を渡る (恐らく兵平岩の奥にあった沢の上流か?) 12時56分 例の標識に従いガレ沢を進む

.jpg)
ケルンを積みましょう 私の積んだケルンを蹴るんじゃないよ
.jpg)
.jpg)
随所に標識が置いてある 斜面をほぼ水平にトラバースする
.jpg)

「石土山登山道13」との文字が残っている 13時05分 ちょっとザレ気味の明るい場所で昼食タイム
13時20分テープが見える藪っぽい茂みを抜けると直ぐに滝のある沢を渡る。水量は少ないので雨が降らなければ水はそんなに流
れていないかも知れない。するとトラバース道が急斜面に入り13時28分立派なヒメシャラの木を過ぎるといよいよ子持ち権現の
尾根部に着いたらしくてトラロープが敷設されていた。
.jpg)
.jpg)
13時20分 昼食のザレ場から藪っぽい場所にテープが続く 藪はすぐ抜け灌木帯のトラバース斜面が続く
.jpg)
.jpg)
13時23分 沢部を通過する 雨の後なので小滝となっている
.jpg)
.jpg)
傾斜が次第に急になる 標識が木に掛かっている ビニール紐や黄色いテープも見える
.jpg)
13時28分 このデカいヒメシャラが子持ち権現西尾根に入る目安となる
鳥越岩からこの尾根取り付き部まで約1時間10分程かかった事になる。
B)尾根取り付き部から子持ち権現山まで 約2時間15分
13時30分から長いトラロープの尾根急斜面を這い上がりが始まり、その後は暫く自然林の急な尾根が続く。尾根を歩く間の
道すがら随所に字が消えた白いアルミの標識を見る事になる。13時57分左手に立つリョウブの木に掛けられた標識が木に喰
われている。すると左上に瓶ヶ森の鋭い南岩壁が木々の間から見え、ここから先の岩場にはワイヤーが敷設されていた。
.jpg)
.jpg)
13時30分 ロープが急傾斜の尾根に伸びる いきなりの急斜面じゃわ トラロープが2本巻かれている
.jpg)
.jpg)
四角いアルミ板は字は既に消えているが標識だろう 自然林の急登が続く
.jpg)
.jpg)
の〜ちゃんはいつもしんがり役を務めてくれる 13時57分 標識がリョウブに食われている
.jpg)
左手の木々の間から瓶ヶ森の大岩壁が見える
.jpg)
.jpg)
14時04分ワイヤーが現れる 14時06分 岩壁に突き当たった様だ 左に瓶ヶ森の断崖
(1の鎖 38m)
14時08分大岩壁の下側に出ると、ワイヤーを頼りに少し右手にトラバースする。するとそこから最初の鎖場が現れる。1段上が
るとV字形に凹んだ急な岩場に沿って更に鎖が延びている。一旦木の根っ子で鎖は終了するのかと思ったがその上にも3段目の鎖が
急な草地に延びていた。14時20分鎖場の上部に出ると背中側に石鎚山が見える。ここから尖った大森山も見えるのだがガスに隠
れている。
.jpg)
.jpg)
14時08分 張られたワイヤーに沿って右手に移動する するといよいよ鎖場のお出ましだ
.jpg)
.jpg)
V字に凹んだ岩の壁に取り付く 黒川ジュニアさんも頑張っとるね
.jpg)
.jpg)
しんがりののーちゃんも上がって来る ここで終わりかと思ったら次がまだ有った
.jpg)
.jpg)
結構長いでガス 写真係りは前へ後ろへと忙しいわ 14時22分 1の鎖が終わり振り返ると石鎚が見えた
(ザレ場のトラバース)約20m
14時22分大岩壁の下側に出る。岩壁の付け根に沿ってロープが敷設されており、これを頼りに足場の薄い急傾斜を20m程トラ
バースしなければならない。13年前はロープが無かったので、ここを避けて右手に岩壁下を伝い進んだ所から尾根を這い上がって
小剣山へ至った記憶がある。
先ずマーシーさんと私が渡って黒河ジュニアさんが行けるかチェックする。念のために黒河ジュニアさんには将来があるのでスワミ
ベルトを付けて貰い、短いスリングとカラビナでロープと体を繋いで安全を確保しここをクリアする。途中ロープの継ぎ目が少し高
い場所にあるので足元に気を付けながらカラビナをセットし直す。
しんがりの「のーちゃん」はこんな場所は慣れているのでジュニアさんをフォローしながら続いて貰う。14時35分トラバース斜
面を全員渡り切ると、ワイヤーとロープがそのまま上側の急斜面に少し続く。上の細尾部が小剣山ピークなのだが、残念ならがそこ
の確認を怠ってしまった。
.jpg)

14時22分 大岩直下のザレ場に出る 岩場に沿ってロープが左手に伸びている
.jpg)
マーシーさんは相変わらずマイペースでスルスルと進む (ロープが2列張られている)

ロープの継ぎ目の場所が少し段差があり危険なのでエントツ山が先行して黒河ジュニアさんをフォローする
.jpg)

足場が薄いので注意が必要だ 後続の黒川ジュニアさんにはスワミベルトとカラビナでロープと繋いで貰っている
.jpg)

の〜ちゃんは身が軽いので結構楽しんでいる トラバースが終わればワイヤーとロープが上に伸びている
(2の鎖) 20m
ザレ場のトラバースが終わると2列になった2の鎖が小剣山ピークへと続くのだが、残念ながらマーシーさんに続いて鎖場のう回路
となっているロープとワイヤー路を通ってしまった様だ。14時37分小剣山から下る鎖場(2の鎖の続き)を辿ってコルに下る。
このコル部は切れ込んだ渡りになっておりサッと過ぎれば何て事ない場所だが中々の切れ込みである。
う〜〜ん2の鎖前半部と小剣山の宿題が残ってしまった。

.jpg)
13年前にピークにあった小剣山の石碑(今回確認せずにピークを下る) 2の鎖後半部 小剣山ピークを下る
.jpg)
.jpg)
コルにはごく短いが蟻の門渡りがある コル部から右手にルートが迂回する
(3の鎖) 20m
コルを過ぎて少し右手に回り込むと14時40分直ぐに次の鎖場が待っていた。ここは急傾斜には変わりが無いが草が生えており
20m程なので直ぐにコル部に着く。すると右手の棚部にオオヤマレンゲが咲いており、代わり交代に写真を撮って引き返す。そこ
からはワイヤーの急傾斜を上がると大岩壁に突き当たる。

.jpg)
「3の鎖」の最初は急な崖状になっている 上の方は地形が安定している
.jpg)
.jpg)
3の鎖が終わるテラスの右手にオオヤマレンゲが咲いていた 鎖が終わるとワイヤーが付けられた急斜面を少し上がる
(4の鎖) 36m (日月の鎖 ?)
14時47分大岩壁の左側に懸かる4の鎖直下に着く。岩壁は結構急だが表面に凹凸があり鎖を頼ればそんなに問題が無い。但し最
下部の5m程が垂直に近く足がかりに乏しい。その上に濡れて良く滑る。慎重に上がり、上から黒河ジュニアさんにアドバイスをし
ながら見守る。彼は高い場所が苦手らしいが、これも慣れでここまで問題無く鎖場や傾斜、トラバース路をクリアしている。この場
所も最初の5m程を苦労した後は余裕で岩場を上がって来る。
.jpg)
.jpg)
ワイヤーを伝って急傾斜を詰める 14時47分 岩壁に「4の鎖」が上に伸びている
.jpg)
最初の4〜5mが急で足掛かりが乏しいのでマーシーさんに黒河ジュニア用スリングを途中に掛けて貰う

.jpg)
「そうそう そんな調子で」と滑り易い難所をクリアする おぉ〜 黒川ジュニアさんも下を向く余裕が出てきたぞ!
.jpg)
.jpg)
「の〜ちゃん スリング回収頼んだぞ〜」「オーケー」 14時58分 しんがり役のの〜ちゃんも崖を上がって来た
15時00分崖の上側の細尾根に着くと天然ヒノキの根元に鎖が一巻して留められている。鎖は古いが結構太くどっしりしているの
で錆(さび)て切れると言った心配はここ暫くは無さそうに感じる。この鎖場は石中寺の解説図では「日月の鎖」と記されている。
.jpg)
4の鎖 末端部 天然檜はほぼ枯れている様だがまだしっかりしている
(5の鎖) 36m
岩場の鎖場を上り切ると正面の尾根に進めるルートが無い。ここは少し左手に傾斜をトラバースするが、ワイヤーが置かれているの
で安全だ。そこを回り込むと15時06分長い「5の鎖」が上に延びている。草が周りに生えていて足元は多少デコボコがある岩場
だが滑り易い。おまけに鎖場の中程は土が斜面の岩を覆い、これ又滑り易い。
.jpg)
.jpg)
ワイヤーに沿って左手に回り込む 15時06分 5の鎖が始まる
.jpg)
急な岩場に土が被り草が生える。そこに鎖が付けられて土が削られたのだろう
.jpg)
.jpg)
黒河ジュニアも今日一日で随分逞しくなった の〜ちゃんは迫力あるステップでグングン這い上がって行く
(ワイヤーに沿って笹の急傾斜が続く) 約20分
15時15分5の鎖を上がり切ると低い笹が一面に生えた急傾斜の尾根となりそこにワイヤーがずっと延びている。急傾斜に喘ぐが
厳しい鎖場の修行を経た辺りの尾根風景は自然林の美しさを感じながら平和に歩ける場所である。
.jpg)
.jpg)
15時15分 鎖場が終わって笹尾根となる 踏み跡に沿ってワイヤーが延ばされている
.jpg)
平凡だが美しい四国の笹尾根が続く
子持ち権現と権現山山頂 (1,677m)
15時36分左上に岩場が見えて、その下に「子持ち権現」が祀られている。やっとここまで辿りついたとホッとする。権現さん
にお詣りの後、大岩の右手から深い笹薮を山頂へ出るが、ここにもワイヤーが敷設されている。
15時42分懐かしい子持ち権現山の山頂に着き休憩を取る。西側は岩黒山からの県境尾根はガスが湧いて奥の筒上山と手箱山が顔
を出す。東側も同じくガスが湧いて瓶ヶ森・男山は見えない。三角点峰「子持」と西黒森が何とか見えている。瓶ヶ森林道が開通し
、今ではこの山の直下まで車で来る事が出来る様になった。この林道が無い時期にはるばる西条・西之川から歩いて見た子持ち権現
山の姿はそれこそ感動ものだったに違いない。
.jpg)
.jpg)
15時36分 ピークが近づくと左手上に権現大岩がある 今日も無事に歩けました ありがとうごぜ〜ます
.jpg)
.jpg)
権現大岩の右手から山頂へ進む ここにもワイヤーがある 県境尾根部はガスが沸いている 手箱山と筒上山
.jpg)
15時42分 子持ち権現山の山頂に到着する 左は瓶ヶ森・男山(石土山) 中央は三角点「子持」 右手奥は西黒森山
.jpg)
.jpg)
の〜ちゃん、黒河ジュニアさん 満足の顔 子持ち権現本懸(ホンガケ)道はまだ最後の鎖場を残す
行程3)子持ち権現山〜三角点「子持」〜瓶ヶ森駐車場 約1時間30分
(6の鎖) 約80m お馴染みの子持ち権現の鎖
15時57分山頂を後にして藪っぽい登山道を東側に下り、踏み跡を辿って北側の鎖場へ移動する。16時02分六の鎖場に着くが、
上を見ると鎖が山頂から延びて来ている。この鎖場は80mとも70mとも言われているので、恐らく山頂部からすると80m程の
長さがあるのだろう。兎に角長い!そして急だ!
15年以上前にここに来た時、高知の登山者から「この鎖を上る事が出来れば北アルプスの鎖場なんてどうって事無いに変わらんぜ」
と言われた。それ以来4〜5回ここを上り下りしている。薄い足場を確保しながら下っていくが辛抱が要る鎖場だ。足場が悪いので
腕力も必要で、怖がる人は自分の足元より下を眺めない方が良い。
一旦鎖場が終わったかと思うがまた更に下へと延びている。所々で補助鎖やロープが掛けられているがあまりアテにしない方が無難
だ。16時16分祠と賽銭箱のある子持ち権現登山口に下り着いた。

.jpg)
下りの鎖場へ向かい踏み跡を下る 北東斜面に向かい笹の中の踏み跡をトラバースする
.jpg)
.jpg)
16時02分 鎖場の降り口に着くと上から鎖が延びてきている ここから6の鎖 約70mの劇下りが始まる
.jpg)
.jpg)
足場が急で滑り易いので注意しながら下る 補助鎖やロープがあるがこれはアテにしない方が良い
.jpg)
.jpg)
目線的にはこんな感じ 16時16分 鎖場の祠に下り着く 最後は長かったなあ
四等三角点「子持」 1,710.04m
一旦瓶ヶ森林道に出て、16時32分ショートカットで上の道路へ出る。さてここで折角この上にある三角点を踏もうって消極的な
メンバーを無理やり平和で快適な瓶ヶ森林道から藪っぽいピークへと向かう。マーシーさんは「瓶ヶ森上の駐車場から快適な登山道
がありますよ」と言うが、そんな回り道は嫌だ。薄い記憶だが確かこのピークは「希望の丘」とか「平和の丘」とか呼ばれていた様
な・・・
で・・・適当に笹の斜面を這い上がって16時42分、山頂の三角点に到着する。そこは希望も平和も無い、只の藪ピークに失望す
る。しかし、国土地理院の三角点閲覧サービスで点名を確認すると、何と「四等三角点・子持」だった。やはりこのピークを踏んで
正解だったのだ。
.jpg)
.jpg)
一旦娑婆に出るがすぐショートカット路に入る ちょっと入口を間違って笹薮を漕いで踏み跡に出る
.jpg)
.jpg)
2度目の娑婆(瓶林)に出るが、更にピークへと向かう 踏み跡は有る様な無い様な・・・テキトーじゃね
.jpg)
.jpg)
16時42分 4等三角点「子持」を踏む え? 嬉しくは無いの? 私ももっとロマンチックな場所だと思ってた
でも、それより子持ち権現ホンガケ道の締め括りは何と言っても石土山(瓶ヶ森・男山)じゃないか! 相変わらず詰詰めの甘い
マーシー・エントツ山コンビだった。
マーシーさんの言ってた「快適な登山道」はそこには存在せず藪を漕いで16時50分瓶ヶ森・上の駐車場に出る。そこから下の駐
車場へデポしている車に帰る。
.jpg)
.jpg)
藪じゃん 16時51分 上の駐車場に出る 「ビールが待っている〜」
小剣山の確認や石土山(瓶ヶ森・男山)の最後の鎖禅譲(7の鎖)を詰めない課題を残して酒飲み達は保冷箱に入れたビールを
抱えてテン場へまっしぐら!。 霧が漂う日で夕日は拝めなかったが、遅くになって星空が美しい夜だった。

.jpg)
保冷バッグに入れたちびたいビールを運ぶ さあさあ 宴会 宴会 反省会? そんなん知らん!
.jpg)
.jpg)
とりあえず乾〜〜杯 お疲れさん 酒飲みからつまみが出される の〜ちゃんは牛肉を仕込んで来ていた
.jpg)
.jpg)
マーシーさんとの〜ちゃんは良く飲み良く食べる ビールが終わったら酒や 酒やで〜〜 知るか〜〜
.jpg)
.jpg)
ワテはコーヒーにポッキーやで いつまでやっとんねん!
エントツ山の山川柳
「星空も 日の出も見ずに テント泊」 (マーシー)
「ザックには テントを入れず 酒を詰め」 (の〜ちゃん)
「初心者は ペグも持たずに テント張り」 (黒河ジュニア)
瓶ヶ森の夜と朝

エントツ山のツェルトと瓶ヶ森の上に輝く星空

西条方面は明るい 薄緑は黒河ジュニアさんのアライテント トレックライズI

笹ヶ峰から朝日が上がる 瓶ヶ森・女山から

朝焼けの石鎚山
瓶ヶ森キャンプと子持ち権現本懸(ホンガケ)道は満足の内に朝を迎えた。 緩いキャンプと厳しい修験の道、硬軟取り混ぜた山歩きも
又いいもんです。この後、黒河ジュニアさん一家を迎えての裏寒風登山へと出発していくのであります
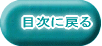
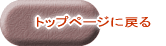


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



